書籍『生きる力を支えるケア──チーム美須賀の挑戦』をご紹介します
美須賀病院の取り組みをまとめた4冊目の書籍、“て・あーて”の実践集『生きる力を支えるケア── チーム美須賀の挑戦』が、看護の科学新社から出版されました。
*編集の重見美代子氏(美須賀病院看護部総師長、当会理事)と、“て・あーて”との出会い&実践のはじまりについては、2022年3月掲載のブログをお読み下さい。
“て・あーて”の知識と技術を実践し、患者さんに生きる活力をもたらした喜びは、看護職のみならず他職種をも巻き込んで「チーム美須賀」としての実践になりました。
本書では、ケアによって患者さんが元気になり、人間らしさ、その人らしさを取り戻していく様子、そしてスタッフの思い、この実践を共有した看護実習体験の状況が、「チーム美須賀」の53名の筆者によって生き生きと綴られています。
看護に携わる方であれば、誰もが看護実践の指南書を読んだ経験があるでしょう。
けれど、患者さんを目の前にして、どれほど役に立ちましたか? また、患者さん一人ひとりの人生や生きがいにはどのくらい関われたでしょうか?
私(当会理事、西山)は40年間臨床の場にいましたが、看護って何だろう? とずっと自問してきました。“その人に寄り添う”ってどうしたらできるのだろうか、と何度悩んだことか……。
もっと早く本書に出会っていたら違った看護ができ、これが看護だと実感できたのではないかと思います。
リスク管理の名のもと、見えなくなっているものを問い直す
以下は、私の実習病院での体験を想起して感じたこと、考えたことです。
「リスク管理とケア」の項目では、センサーマットの効果への疑問やストレスを生み出している状況から、センサーマット廃止に至った経緯と、転んでも骨折しないように工夫しながらADLを拡大していった事例が掲載されています。
私もリスク管理という名のもと、センサーマットが床に置かれることが多くなった現状を目にしました。
患者さんの中には、床に足をつくと看護師が来るとわかり、センサーを踏まないように跨いでトイレに行ったり、ベッドの枕元の柵の間から降りようとしたりする場面もあり、この高さから落ちなくて良かったと胸を撫でおろすこともしばしば。何のためのセンサーマットかと、筆者の思いに共感しました。
また、医原性の廃用症候群について、夜中に何度もトイレに行きたいとナースコールをしていた患者Aさんに「さっき行ったばかりなのに」「オムツでしていいですよ」と対応されていました。
Aさんは排泄後のオムツを気持ち悪いと感じ、自分で外して床頭台の上に置いたのです。翌朝スタッフが汚れたオムツを見て、「こんなところに置いて」と抑制着を着せてしまいました。その結果、Aさんはベッド上で生活することになってしまったのです。看護って何? と考えさせられます。
本書を読み進めていくと、廃用症候群で美須賀病院へ入院してきた患者さんの前院での状況がこの場面と同じだ、と思うことが多々ありました。そんな患者さんが、「チーム美須賀」の手にかかるとぐんぐん回復していく様は、本当に見事としか言いようがありません。
“手”の持つ可能性を見直す
清拭についても一石を投じています。最近では清拭にディスポタオルを使用する施設が増えています。すぐに冷えてしまうタオルに「冷たい」と患者さんが小さな声を発しても、「すぐに済みます」と言いながら手を動かしてそそくさと清拭を行う看護師の手。その手から、患者さんの冷えた肌が伝わらないのだろうかと疑問に感じます。
患者さんにとって気持ちの良いケアが提供される場面がどんどん減っている現状に、危機感を持つべきではないでしょうか。本来看護師は、自然治癒力に働きかけ、回復力・免疫力を上げていくことが責務です。熱いタオルでの熱布清拭、オイルを使ってむくんだ手足を優しくマッサージする──これらの手の持つ可能性を見直し、患者さんの思いに近づく「手を用いたケア」の実践が、本書のどのページからも伝わってきます。
看護って何だろう? 自分のやりたい看護は? と試行錯誤している方、患者さんへの関わりが難しいと感じているあなたの背中を押してくれる本です。
介護やリハビリスタッフなど、看護師以外の方にも手に取って欲しいと思います。
「チーム美須賀」だからできたのでは、と感じる方もいるかもしれません。
でも、今のままでいいのですか? あなたの看護人生の原点はどこにありますか?
まだ間に合います。患者さんの声に耳を傾けて、“手”を用いてケアしてみませんか。
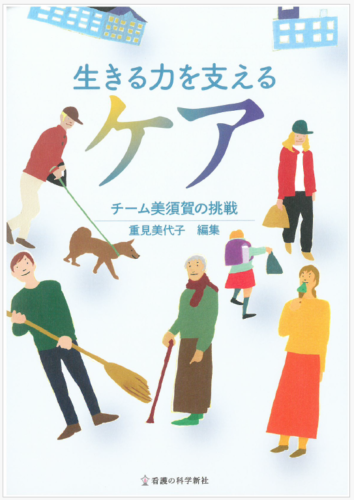
(西山みち子 記)
『生きる力を支えるケア ──チーム美須賀の挑戦』(看護の科学新社)
*医書取り扱い書店のほか、Amazon, Rakutenでもお買い求めいただけます
2025年2月24日
イベントのお知らせ&ご報告
過去の記事
寄付のお願い
被災地の看護師の夢を共有し、その実現に向かって皆様のあたたかなご支援をお願いいたします。
お振り込み方法
1.郵便局の場合
口座記号番号:00120-8-596287
口座名称:ハウス・てあーて
2.銀行からゆうちょ銀行の場合
店名(店番):〇一九店(019)
口座種別:当座
口座番号:0596287

